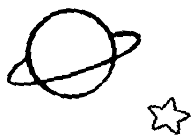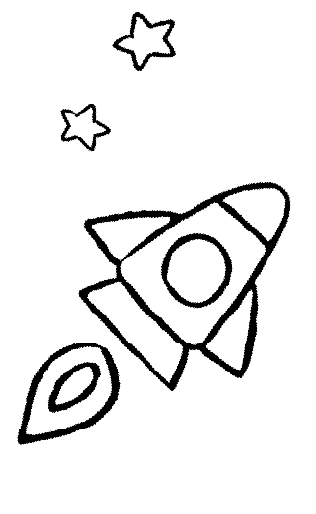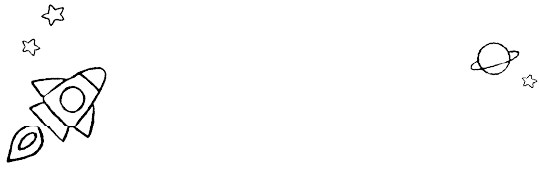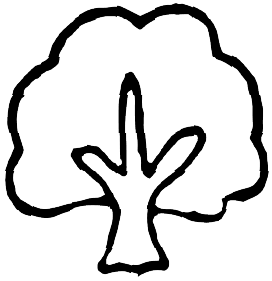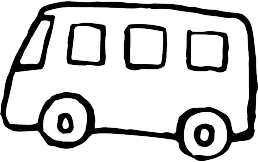【全盲の研究者、守井清吾が教える】生成AI集中講座
~視覚障害者の「できない」を「できる」に変える~
生成AIの概要から実践まで
~単なる道具ではない!生成AIを相棒にしよう~
視覚障害者にとって、誤字脱字の修正や画像・ビジュアル情報の入手は、これまで大きな困難を伴いました。しかし、生成AIの登場は、これらの課題を克服し、新たな可能性を切り開いています。
With Blindで講師を務める守井清吾は、生成AIの有料プランをいくつも契約し、コーディング、報告書作成、資料作成など、本業と副業の仕事の様々な場面で活用しています。
視覚的に確認できないエクセルのレイアウト調整や資料の色使いなども、生成AIで調整しています。
この講座では、守井が実践で培ったノウハウを紹介し、視覚障害者の就労状況の底上げに貢献します。
「生成AIって最近よく聞くけど、実際何ができるの?」
「視覚障害があるけど、生成AIは使えるのかな?」
そんな疑問をお持ちのあなたへ。
全盲の研究者、守井清吾が生成AIの世界へご案内します!
この講座では、生成AIの基本的な知識から、視覚障害のある方でも活用できる実践的な使い方までを、デモンストレーションも行いながら、わかりやすく解説します。学生から社会人まで、誰もが理解できるように、やさしい言葉で講座を進めていきます。
講座のポイント
- 視覚障害者フレンドリーな解説: スクリーンリーダーや音声認識など、支援技術との連携方法も紹介します。
- 具体的な活用例: 守井自身の経験を交えながら、日常生活や仕事で役立つ生成AIの活用方法を具体的に紹介します。
- 就労に役立つノウハウ: コーディング、報告書作成、資料作成など、仕事で使える生成AI活用術を伝授します。
- 著作権問題にも言及: 生成AI利用における著作権問題についても解説し、安心して使えるようにサポートします。
講師紹介
守井清吾

全盲の研究者。5歳で左目を失明し、その後右目も徐々に悪くなり、全盲に。数々の困難を克服し、富山大学教育学部を卒業後、同大学院生命融合科学研究部で工学博士号を取得。2015年に株式会社インテックに入社し、現在は先端技術研究所で画像情報解析技術や触覚/聴覚融合インタフェースの研究に従事。
アニメ、ゲーム、音楽鑑賞を楽しみながら、研究開発やプログラミングにも精力的に取り組んでいます。
開発したスマホアプリ「これなにメモ」や、生成AIを使った画像作成/認識体験のためのデモプログラムを通して、視覚障害者の情報アクセス手段の向上を目指しています。
オンラインスクールWith Blindの講氏としては、小学生から高校生までを対象とした算数数学の講座や、プログラミングの講座をいくつも担当しています。
「生成AIは、視覚障害のある私たちにとって、可能性を広げてくれる強力なツールです。一緒に生成AIの世界を探求しましょう!」
講座で学べること
- 生成AIとは?: LLMをはじめ、画像生成AI、音声生成AIなど、様々な種類の生成AIについて学びます。
- デモ: PC操作を通して、生成AIの動作を体験できます。
- 守井清吾の生成AI活用術:
- LLM:
- 講義のタイトルや教材作成
- 報告書作成
- プログラミング支援(GitHub Copilot)
- エクセル、資料のレイアウト調整、色使い
- ChatGPT(ボイスモード):
- 雑談相手
- 情報収集
- ChatGPT(ボイスモード/カメラモード):
- パッケージの読み上げ
- カードゲームのサポート
- LLM:
- 生成AIと著作権: 日本俳優・声優団体発表の声明を参考に、著作権問題について解説します。
- 質疑応答:
- 視覚障害者の支援制度、能力開発、趣味、就労など、多岐にわたる質問を受け付けます。
講座概要
- 日時:2025年4月26日(土)20時から22時まで
- 参加費:1,650円(税込み)
- 募集人数:制限なし
- 対象者:視覚障害のある方、生成AIに興味のある方
- 場所:オンライン(Zoomを使用)
申込方法
こちらの申込フォームから必要情報を入力して申し込みを完了させてください。
お問い合わせ
一般社団法人With Blindのお問い合わせフォームにご連絡ください。
一般社団法人With Blindについて
「見えても、見えなくても、ともに。」を合言葉に、視覚障害のある方のITスキル向上や学習支援を行っています。
皆様のご参加をお待ちしております!